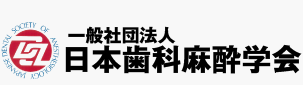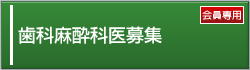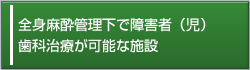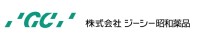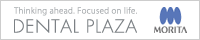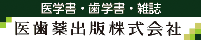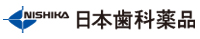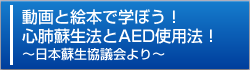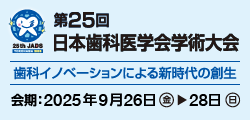理事長挨拶

一般社団法人 日本歯科麻酔学会
理事長 宮脇 卓也
2023年10月から当学会の理事長を拝命しております。理事長として、関係各位さらにこのホームページを見ていただいている全ての皆様に、ご挨拶させていただきたく存じます。私は、当学会が歯科医療の発展に貢献し、それが歯科患者の皆様の口腔の健康に、さらに全身の健康につながり、国民の皆様のWell-beingに貢献していると信じております。そんな当学会を、より多くの皆様に、より深く知っていただきたいと思っております。
当学会、一般社団法人 日本歯科麻酔学会は1973年9月に設立されました。発祥は1966年に発足した「歯科麻酔懇談会」ですので、学術研究団体としては50年以上の歴史を有しています。世界的には、歯科医師William Thomas Green Mortonによって、世界で初めて「麻酔(全身麻酔)」が公開されたのが1846年ですので、歯科医師による「麻酔(全身麻酔)」の歴史は170年以上になります。
歯科麻酔とは、安全で痛みのない快適な歯科医療を提供するための専門領域であり、さらに、口腔顎顔面の「痛み」の病気を治療する専門領域です。当学会は、その専門的知識および技能をもった専門家の集まりであり、診療、教育、研究、開発、普及、および啓発することによって、歯科医療の発展および地域社会の福祉に貢献することを使命にしております。
具体的に私たちは、患者さんに障がいがあり、歯科治療が苦手な場合、ストレスのないように歯科治療を受けることができる「行動調整(鎮静または全身麻酔)」を専門としています。大きな病院では、歯科口腔外科の手術を受けられる患者さんが、安全に手術を受けることができる「歯科医療における全身麻酔」を専門としています。また、歯科治療に対する不安や、一種の恐怖を持っておられる患者さんが、快適に歯科医療を受けることができる「鎮静」を専門としています。高齢の患者さんや高血圧、心臓の病気などを持っておられる患者さんが、安全に歯科治療を受けることのできる「全身管理」を専門としています。また、歯科治療中に突然、患者さんの気分が悪くなったり、意識がなくなってしまった時、すぐに対応して患者さんの安全を確保する「緊急処置」を専門としています。さらに専門診療部門として、むし歯でも歯周病でもなく、歯科の病気が原因でない、原因がよくわからない口、顎、顔の痛みに対する「歯科ペインクリニック」を専門としております。このように通常の歯科診療で困っておられる患者さんと歯科医を支援する、縁の下の土台の部分が私たちの役割です。
現在、当学会の会員は約3,000名で、全国で活躍しています。また、歯科麻酔専門医、認定医、登録医、認定歯科衛生士の資格があり、これらの有資格者は当学会のホームページで公開しています。近隣の当学会会員にご相談いただければ、きっとお役に立つことができると思います。
歯科医療はどんどん発展しておりますが、私たちの歯科麻酔の領域も日進月歩しています。私たちは学術研究団体として、世界を主導できるよう学術研究を推進し、常に最先端の専門的な診療を提供できるよう、会員の研修を奨励しております。今後も、私たち当学会の会員は、歯科医療の発展に貢献し、地域社会の福祉、国民のWell-beingに貢献してまいる所存です。